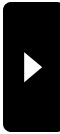2013年05月22日
鬼ブログ 410
(5月22日 産経ニュース)
■50冊超の古書や船箪笥も 歴史的流れ知る貴重な資料
江戸時代後期、弘化元(1844)年創業の香川県土庄町のしょうゆ製造販売会社「ヤマトイチ」を営む大森家から、地元・大部(おおべ)地区の港に波止場を造営した際の寄進帳とみられる台帳や、得意先との取引内容を記した売掛帳(うりかけちょう)など幕末から明治期の古文書が見つかった。50冊を超える古書も確認され、町教委は「古文書は小豆島のしょうゆや村落の歴史的流れを知る上で貴重。地方の商家の蔵書も興味深く、詳しく調べる価値がある」としている。
同社によると、寄進帳と売掛帳のほか、銃や大砲の扱いを図解付きで解説した江戸期の専門書「砲術訓蒙」や冠婚葬祭のあいさつ言葉などの文例集「商人書輪便覧」、明治期に発行された史書「校正 日本外史」などが、大森家の土蔵から見つかった。船箪笥(ふなだんす)や香時計(こうどけい)、硯(すずり)と筆を組み合わせた携帯用筆記具の矢立(やたて)といった生活用具もあった。
寄進帳とみられる古文書「波戸奇進長(帖)」は幕末の慶応年間につづられたもので、波止場を造る際の住民からの寄付金や都合した作業員について記録。また、売掛帳は安政から慶応年間のもので、得意先に販売したしょうゆの量や米の値段などが記載されていた。
同社は江戸期から商品を港から船で岡山県に運んで行商していたといい、見つかった古文書から当時のしょうゆの販路をたどることもできそうだ。大森勝輔社長は「将来的にはもろみ蔵をギャラリーに改装して得意先や郷土史愛好家が閲覧できるようにしたい」と話している。
同社は昭和51年の台風17号による豪雨で発生した土砂災害でもろみ蔵を含む工場全体が損壊するまでは自社でしょうゆを醸造していた。現在も委託醸造のしょうゆ商品を先祖に習って岡山県南部を主な販路に行商している。
すごく興味がありますねー!歴史好きというわけではなくとも、何となく見てみたいと思う気持ちが、わいてきます。
数年前ですが、ほんっとに偶然に古い個人宅で倉庫展が開かれていて、入ったことがあります。戦前の生活用品や、明治時代の人の手習い帳などなどが飾ってありました。博物館とかで飾ってあるものではなく、生活感が感じられるほど身近でロープ1本で仕切られていたのにはびっくりした記憶があります。
携帯筆記用具とか、香時計とか今は無き道具に、時代時代の人の知恵を感じます。ぜひ、研究結果の記事も待っています!!
■50冊超の古書や船箪笥も 歴史的流れ知る貴重な資料
江戸時代後期、弘化元(1844)年創業の香川県土庄町のしょうゆ製造販売会社「ヤマトイチ」を営む大森家から、地元・大部(おおべ)地区の港に波止場を造営した際の寄進帳とみられる台帳や、得意先との取引内容を記した売掛帳(うりかけちょう)など幕末から明治期の古文書が見つかった。50冊を超える古書も確認され、町教委は「古文書は小豆島のしょうゆや村落の歴史的流れを知る上で貴重。地方の商家の蔵書も興味深く、詳しく調べる価値がある」としている。
同社によると、寄進帳と売掛帳のほか、銃や大砲の扱いを図解付きで解説した江戸期の専門書「砲術訓蒙」や冠婚葬祭のあいさつ言葉などの文例集「商人書輪便覧」、明治期に発行された史書「校正 日本外史」などが、大森家の土蔵から見つかった。船箪笥(ふなだんす)や香時計(こうどけい)、硯(すずり)と筆を組み合わせた携帯用筆記具の矢立(やたて)といった生活用具もあった。
寄進帳とみられる古文書「波戸奇進長(帖)」は幕末の慶応年間につづられたもので、波止場を造る際の住民からの寄付金や都合した作業員について記録。また、売掛帳は安政から慶応年間のもので、得意先に販売したしょうゆの量や米の値段などが記載されていた。
同社は江戸期から商品を港から船で岡山県に運んで行商していたといい、見つかった古文書から当時のしょうゆの販路をたどることもできそうだ。大森勝輔社長は「将来的にはもろみ蔵をギャラリーに改装して得意先や郷土史愛好家が閲覧できるようにしたい」と話している。
同社は昭和51年の台風17号による豪雨で発生した土砂災害でもろみ蔵を含む工場全体が損壊するまでは自社でしょうゆを醸造していた。現在も委託醸造のしょうゆ商品を先祖に習って岡山県南部を主な販路に行商している。
すごく興味がありますねー!歴史好きというわけではなくとも、何となく見てみたいと思う気持ちが、わいてきます。
数年前ですが、ほんっとに偶然に古い個人宅で倉庫展が開かれていて、入ったことがあります。戦前の生活用品や、明治時代の人の手習い帳などなどが飾ってありました。博物館とかで飾ってあるものではなく、生活感が感じられるほど身近でロープ1本で仕切られていたのにはびっくりした記憶があります。
携帯筆記用具とか、香時計とか今は無き道具に、時代時代の人の知恵を感じます。ぜひ、研究結果の記事も待っています!!
Posted by うどん≠讃岐 at 15:37